【書評・要約】Amazonの成功を支える“逆算思考”──『Working Backwards』を読んで学んだ、仕事を変える思考法

はじめに──なぜ日本の仕事は“進まない”のか?
毎日残業しているのに、「全然仕事が進まない」「うまくいかない」と悩んでいる社会人の方は多いのではないでしょうか。
たとえば、
- 「会議が長いのに何も決まらない」
- 「関係部署との調整ばっかり」
- 「せっかくできた商品・サービスが顧客に全く刺さらない」
──こうした状況に、心当たりはありませんか?
特に歴史ある日本企業に勤めている方なら、こうした“なんとなく進まない空気”に違和感を覚えているはずです。
一方で、アメリカのBig Tech──たとえばAmazon、Google、Metaといった企業は、次々に新しいサービスを生み出し、世界中にインパクトを与えています。なぜ、あれほどのスピードと精度で革新を起こせるのか?
その秘訣の一端を、Amazonの元幹部であるコリン・ブライアーとビル・カーが明かしたのが、今回紹介する一冊『Working Backwards(ワーキング・バックワーズ)』です。
本書は、単なる成功物語ではありません。Amazonが「どうやって考え、どうやって組織を動かし、どうやって顧客に刺さる製品を届けてきたのか」を、私たちの日常業務にも応用できるレベルで解説しています。
この記事では、特に「これは日本の企業文化や私たちの働き方にこそ必要だ」と私が感じたエッセンスをご紹介します。
ターゲット読者:こんな人におすすめ
- 「会議が多いのに結論が出ない」と感じる人
- 採用や人材育成に課題を感じているマネージャー
- プロダクト開発の進め方に迷っている企画・開発担当者
- ベンチャー・スタートアップで戦略を模索している方
1. “理想の顧客体験”から逆算する「Working Backwards」
本書のタイトルでもある「Working Backwards」は、Amazonがすべてのプロジェクトにおいて大切にしているアプローチです。
どうやるのか?
Amazonでは新製品を開発する際、最初に着手するのは、「完成後のプレスリリース(PR)」と「よくある質問(FAQ)」の作成です。
これは、「この製品は誰の、どんな課題を、どう解決するのか?」という“顧客価値の原点”を、チーム全員が共有するための手法です。
そして、Amazonの開発文化の象徴でもある「Working Backwards(顧客視点からの逆算思考)」の中核をなしています。
なぜPR/FAQが重要なのか?
PR/FAQを書くためには、サービスの完成形を“ありありと”想像できていなければなりません。つまり、アイデア段階のふわっとした構想を、誰が読んでも「これなら買いたい」「これが欲しかった」と思えるレベルにまで落とし込む必要があるのです。
この作業を通じて、
- 実現に向けて乗り越えるべき課題や障害
- 関係部門との連携に必要なこと
- 顧客が本当に求めている体験とは何か
──が、具体的に“見える化”されます。
これにより、関係者全員の足並みを揃えたうえで、最短距離で開発を進めることができます。
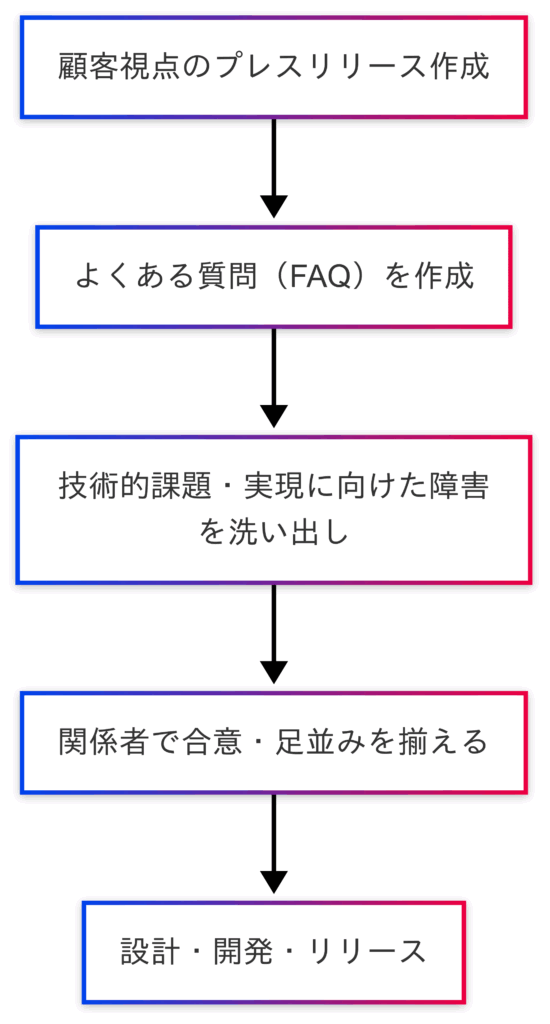
例えば:Kindleの誕生もPR/FAQから始まった
電子書籍リーダー「Kindle」も、PR/FAQから生まれました。Amazonが掲げた顧客価値はこうです。
- 「1分以内に本がダウンロードできる」
- 「1週間以上バッテリーがもつ」
これらは当時の技術水準では実現困難とも思えるものでしたが、「顧客が本当に望んでいる理想」を先に描いたことで、開発チームは明確なゴールを持って行動できました。
結果として、Kindleは他社にはないユーザー体験を実現し、電子書籍市場で圧倒的なポジションを築きました。
2. 「ナラティブ文化」が無駄な会議をなくす

Amazonでは、パワーポイントのプレゼンは禁止されています。代わりに使われるのが「6ページのナラティブ文書」です。
これは、担当者がプロジェクトの背景、課題、提案、根拠を文章で論理的にまとめたもので、会議冒頭に全員で黙読します。担当者はパワーポイント資料の見た目や実際のプレゼンによる「幻覚」に頼ることはできません。逆に、これを準備していく過程で企画内容は「中身のある」ものになります。
ここがすごい
- 全員が共通の前提で議論できる
- 文章にすることで「中身のある」企画に精査できる
- 議論の質が爆発的に上がる
3. 「シングルスレッドチーム」で集中とスピードを生む

Amazonでは、大きな組織横断型チームではなく、1つのプロジェクトに専念する「シングルスレッドリーダー」と小さな専属チームを置きます。
これにより、「他の業務に時間を取られて進まない」という日本企業にありがちな問題を回避しています。
具体例
- Prime Videoの立ち上げも、独立した小さなチームでスタート
- 他部門との調整より、顧客価値の創出に集中できる
4. 採用は「バー・レイザー」が担保する
Amazonでは「バーレイザー制度」という採用基準維持の仕組みがあります。通常の面接官に加え、高い水準での採用判断を行う“バー・レイザー”が必ず面接に関わります。
この制度は、採用基準が徐々に緩くなる“カルチャードリフト”を防ぎ、強いチームを維持する鍵になっています。
5. 成果ではなく「入力(Input)」を重視する指標文化
Amazonでは、売上や利益といった“結果”ではなく、「顧客がカートに入れるまでの時間」「配送エラー率」など、自分たちでコントロールできる“インプット”をKPIとします。
6. 実際のプロダクトで「文化」がどう活きたか
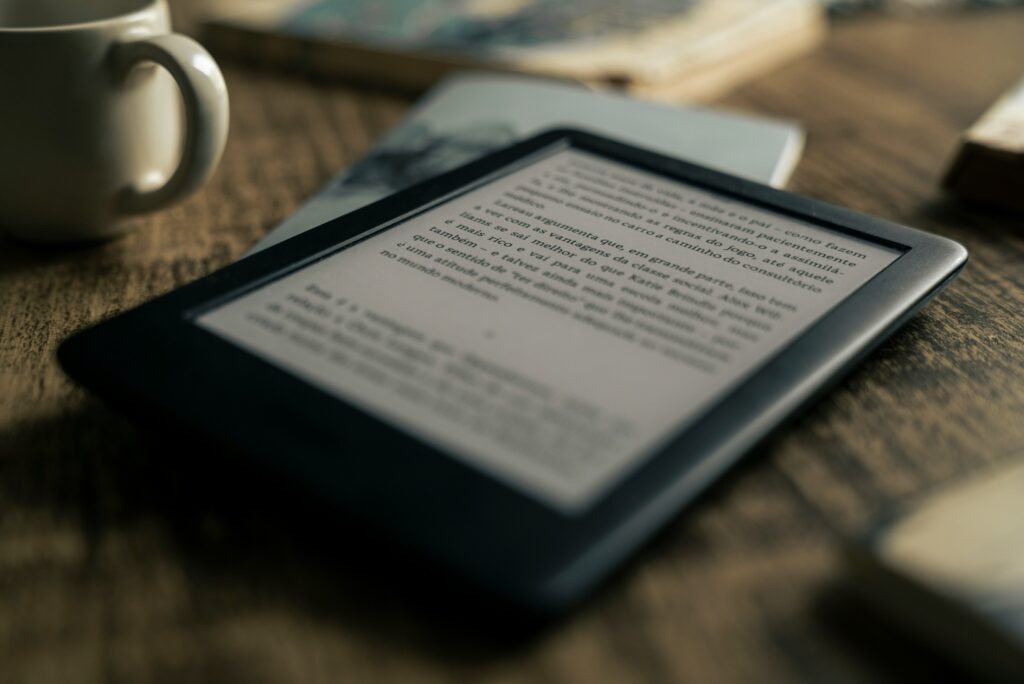
後半では、以下の製品開発を通して、上述の思想がいかに実践されてきたかが描かれます。
- Kindle:Working Backwardsで「持ち運べる図書館」を構想
- Amazon Prime:独立チームが“配送の価値”に着目し逆算
- AWS:FAQから始まり、開発者に徹底して寄り添う設計へ
- Prime Video:ナラティブ文化で意思統一し、迅速に立ち上げ
これらのケースは、ただの成功談ではなく、読者が自社・自分にどう応用できるかを考えるヒントに満ちています。
おわりに:この本が変えてくれる“働き方の視点”
『Working Backwards』を読み終えたとき、「これはAmazonだけの話ではない」と確信しました。
- 顧客を起点に考える
- 無駄な会議をなくす
- 小さなチームで素早く動く
こうした考え方は、私たちの日常業務やチームマネジメントにすぐに取り入れられるものです。
「もっとよく働きたい」「変化を起こしたい」そう思っているすべての社会人に、ぜひ手に取ってほしい1冊です。

