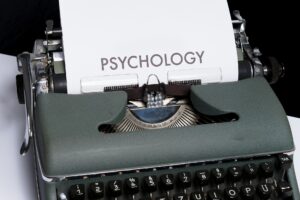世界の一流は休日に何をしているのか?|疲れを取る休日の技術とは?【書評・要約】

はじめに
「週末がいつも疲れて終わる」「もっと効率よく休めたらいいのに」——
そんなふうに感じたことはありませんか?
越川慎司氏の著書『世界の一流は休日に何をしているのか』は、日本人の“休み下手”を解決するヒントに満ちた一冊です。この記事では本書のエッセンスをわかりやすく要約し、疲れを取る“戦略的休日”の取り入れ方を紹介します。
なぜ日本人は疲れているのか?
日本では「働き方改革」により残業の上限が設けられましたが、かえって「仕事が終わらない」「休んでも疲れが取れない」と感じる人が増えています。
その背景には、“個人依存”の働き方文化があります。
欧米では「仕組みで休む」ことが主流。上司が休んでも仕事が回るよう設計されています。
一方、日本では「〇〇さんがやっているから帰れない」「自分がやらないと終わらない」といった属人的な働き方が今も残っています。
さらに問題なのが、「上司が休まないと部下も休みにくい」という空気感です。
例えば、ある営業部では、上司が休日にSlackを確認しており、返信しないと「やる気がない」と捉えられるそうです。これはもはや“休み”とは呼べません。
こうした文化が蓄積されることで、休むことを躊躇してしまうのです。
世界と日本の休日の違い

本書では、「日本人は疲れたから休む。世界の一流は疲れる前に休む」と明快に述べられています。
日本では休日を「静的な休息の時間」と捉えがちで、寝だめや動画視聴で過ごしてしまうことも。しかし、休んだはずなのに月曜には疲れが残っている……という経験は多いのではないでしょうか。
一方で、世界の一流たちは**「動」の休み方**を実践しています。
例えば、著者がマイクロソフト副社長から聞いたのは、ハーレーでのツーリング体験。風を切りながら走ることで、日常では得られない感覚や思考の解放を手に入れるのだそうです。
自己効力感を高める「ワークライフハーモニー」とは?

「ワークライフバランス」は、天秤のようにどちらかが重くなるともう一方が犠牲になるという考え方です。
しかし著者は、「仕事と生活は対立するものではなく、調和させるべきだ」と説きます。これが「ワークライフハーモニー」という考え方です。
重要なのは、休日に“自分はできる”という感覚=自己効力感を育てること。
- 簡単な目標を設定し、小さな達成感を得る
- 新しいことをとりあえずやってみる
- 人とのつながりを大切にする
- 自己省察の時間をもつ
これらの体験を休日に取り入れることで、自分に対する信頼感(自己効力感)が高まり、翌週の仕事にも良い影響を与えます。
ここで言う“自己効力感”とは、「他人よりすごい」ではなく、「自分ならできる」という静かな自信。他人との比較が不要で、行動のハードルも低いのが特長です。
土曜日と日曜日の具体的戦略
著者は「土曜日と日曜日は、別々の機能を持たせるべき」と述べています。
- 土曜日=チャレンジデー
→ 新しい体験、学び、人とのつながりを意識して「教養」を得る - 日曜日=リフレッシュデー
→ 軽い運動や瞑想、読書などで「休養」に集中する
その準備は金曜の午後から始まります。
- 休日の計画を立てる
- 翌週のToDoを整理
- あえて仕事を“途中で終わらせる”(ツァイガルニク効果)
これにより、休日中にも自然とクリエイティブな発想やモチベーションが生まれます。
おわりに:休み方が変われば、人生が変わる
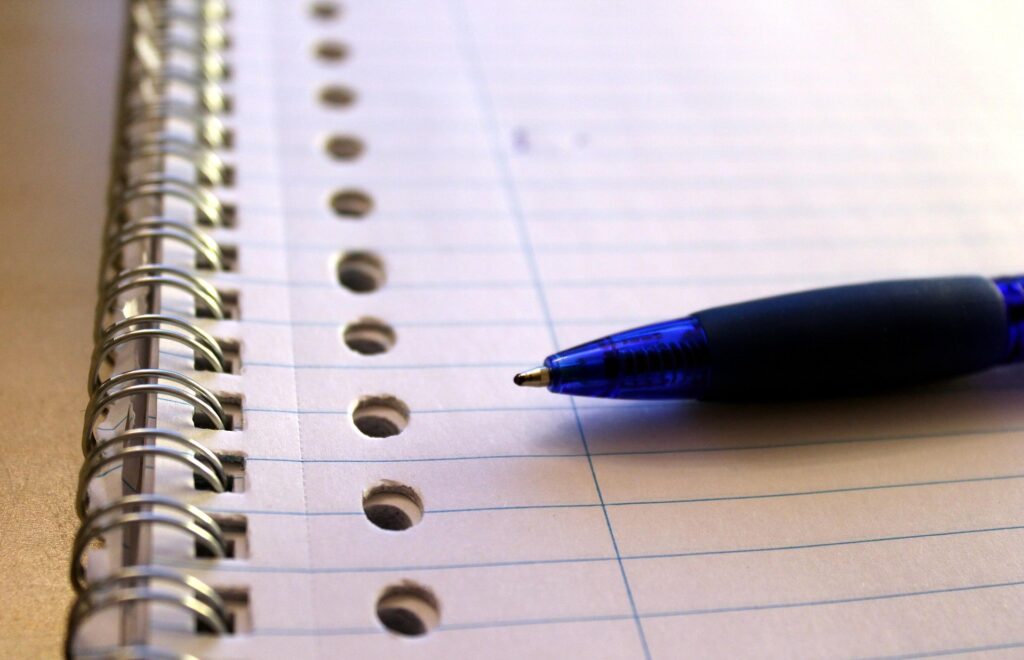
「最近、休日に何をしていたか思い出せない」
「土日が終わっても疲れが抜けない」
「自分の時間がない」
そんな方にこそ、本書を手に取ってほしいです。
休み方はスキルであり、技術です。 正しい休日の過ごし方を知ることで、自分のパフォーマンスと幸福感をコントロールできるようになります。